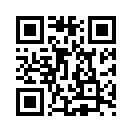2013年03月28日
研究会の編成を再提案します
FSRJの主要な方々へ、奥です。
5年ほど前になるかと思います。FSRJで将来構想や社会との接点を考える研究小部会を作って勉強会を始めたらどうかと提案したことがありました、首都圏を中心として数人でもよいからと。
しかし良い感触は戻ってきませんでした。
一方で、原田幸明氏を中心にした未踏科学技術協会のエコマテリアルフォーラムでは、2050年を見通した「ベッセマー+200の鉄と社会」フォーラムを2年ほど前から始めています。
ここ数年のあいだにFSRJも、皆さんの先見とご努力により、高分子学会や廃棄物資源循環学会と協調する新たな時代に踏み入ったようです。そこで、立ち消えた研究会あるいは検討会の構想を、我々の将来ビジョンを形成する場として再考再編したらどうかと提案します。
ベッセマーフォーラムの文章をモデルにして、幼稚ですが、"プラスチック+150の社会"という仮タイトルで呼び掛け文を考えてみました(添付書面をご参考に)。
高分子学会GC研究会へ呼びかけして協働作業するのは当然でしょうね。それらの準備を首都圏の方々を中心にご検討いただければありがたいと思います。私は呼びかけ人ですからお手伝いさせていただきましょう。
3月の幹事会での議題にしていただけませんか。
ご意見をお待ちします。
(A)参考資料: 2013-2-20 シンポジウム開催の趣意書からコピー
2013-2-20 つくば国際会議場
主催: 未踏科学技術協会・エコマテリアルフォーラム
ベッセマー+200の鉄と社会
1856、H.Bessemer は、当時のパドル法に代わる空気底吹き法による鋼の製造方法を確立しました。以来、鋼の大量生産が可能になり、現在では年間10数億トンもの鉄鋼材を生産するにいたっております。いっぽう、このベッセマーの大発明から約200年後の2050年に向けて、生産量は著しく増加し、高品位の原料調達が困難になることも考えられます。また、世界的に大幅なCO2排出削減による制約も考えられます。このような将来社会において、ベッセマーの発明以来続いてきた高炉・転炉法による製法は、今後どのように変化するのでしょうか。
2010年に発足した「ベッセマー+200の鉄と社会」WGでは、2050年の社会において必要とされる素材(鉄鋼)の使われ方や、求められる製鉄製鋼法などについて自由な議論を行い、今後の材料科学の開発課題に関する有用な示唆を抽出したいと考えています。
第7回となる本シンポジウムでは、将来の社会(宇宙建造物、超高層建築物等)で求められるであろう素材(鉄鋼材)の機能をテーマに議論いたします。さまざまな立場の方々のご参加とご意見を期待しております。
――――――――――――――
(B)上記の文章をプラスチック関連の集会呼び掛け文に読み替えたもの
プラスチック+150の社会
1909年、Leo Baekelandは、フェノールとホルマリンを原料とする化学合成法によってフェノール樹脂を製造する方法を発明しました。有機材料として木材などの天然材料を使用していた時代に革命が起こったのです。この製造法は、鉄鉱石を高温還元して鉄原子塊である鉄鋼を製造するのとは大きく異なり、低分子の有機物質から高分子素材を製造するという人類の快挙でありました。それ以降は高分子化学が台頭して化学産業の発展につながり、数多の高分子が発明されてプラスチック材料の大量生産が可能になりました。現在では世界で年間1億数千万トンものプラスチックが生産され、嵩高さでは鉄鋼の総生産量に匹敵するまでにいたりました。
いっぽう、プラスチックの大発明から約150年後の2050年に向けて、著しく増加するプラスチック生産量を賄う原料資源の調達はかなり困難になると考えられています。有限量の化石資源に代わると考えられてきたバイオマス資源も現在の巨大な需要量の僅かな部分しか補えず、いっぽう世界的規模でCO2排出削減の制約も受けるでしょう。この将来社会において合成高分子の材料調達はリサイクルも含めて今後どのように変化し、また変えなければならないのでしょうか。
高分子とプラスチックの製造使用に関る者、リサイクルにより資源再生にかかわる者が協力して、2050年の社会を目標に置き議論する必要を強く感じます。そこでは、2050年に必要とされるプラスチックをどう作りどう使うのか、資源の再生に欠かせないリサイクル技術と社会のネットワークを含めて自由な議論を行い、将来のプラスチック社会の姿を真剣に見つめなければなりません。
さまざまな立場からのお考えとご意見を聞かせていただきたく存じます。
記:
1.FSRJと高分子学会GC部会がコアとなって共同発議し、集会準備会を立ち上げる。本年2013年の秋を目標に準備を進めたらどうか。
2.この合同企画は技術的研究集会とは別個に考えるのか、それとも関連させて考えるのか。
3.毎年1回は開催したらどうか。
5年ほど前になるかと思います。FSRJで将来構想や社会との接点を考える研究小部会を作って勉強会を始めたらどうかと提案したことがありました、首都圏を中心として数人でもよいからと。
しかし良い感触は戻ってきませんでした。
一方で、原田幸明氏を中心にした未踏科学技術協会のエコマテリアルフォーラムでは、2050年を見通した「ベッセマー+200の鉄と社会」フォーラムを2年ほど前から始めています。
ここ数年のあいだにFSRJも、皆さんの先見とご努力により、高分子学会や廃棄物資源循環学会と協調する新たな時代に踏み入ったようです。そこで、立ち消えた研究会あるいは検討会の構想を、我々の将来ビジョンを形成する場として再考再編したらどうかと提案します。
ベッセマーフォーラムの文章をモデルにして、幼稚ですが、"プラスチック+150の社会"という仮タイトルで呼び掛け文を考えてみました(添付書面をご参考に)。
高分子学会GC研究会へ呼びかけして協働作業するのは当然でしょうね。それらの準備を首都圏の方々を中心にご検討いただければありがたいと思います。私は呼びかけ人ですからお手伝いさせていただきましょう。
3月の幹事会での議題にしていただけませんか。
ご意見をお待ちします。
(A)参考資料: 2013-2-20 シンポジウム開催の趣意書からコピー
2013-2-20 つくば国際会議場
主催: 未踏科学技術協会・エコマテリアルフォーラム
ベッセマー+200の鉄と社会
1856、H.Bessemer は、当時のパドル法に代わる空気底吹き法による鋼の製造方法を確立しました。以来、鋼の大量生産が可能になり、現在では年間10数億トンもの鉄鋼材を生産するにいたっております。いっぽう、このベッセマーの大発明から約200年後の2050年に向けて、生産量は著しく増加し、高品位の原料調達が困難になることも考えられます。また、世界的に大幅なCO2排出削減による制約も考えられます。このような将来社会において、ベッセマーの発明以来続いてきた高炉・転炉法による製法は、今後どのように変化するのでしょうか。
2010年に発足した「ベッセマー+200の鉄と社会」WGでは、2050年の社会において必要とされる素材(鉄鋼)の使われ方や、求められる製鉄製鋼法などについて自由な議論を行い、今後の材料科学の開発課題に関する有用な示唆を抽出したいと考えています。
第7回となる本シンポジウムでは、将来の社会(宇宙建造物、超高層建築物等)で求められるであろう素材(鉄鋼材)の機能をテーマに議論いたします。さまざまな立場の方々のご参加とご意見を期待しております。
――――――――――――――
(B)上記の文章をプラスチック関連の集会呼び掛け文に読み替えたもの
プラスチック+150の社会
1909年、Leo Baekelandは、フェノールとホルマリンを原料とする化学合成法によってフェノール樹脂を製造する方法を発明しました。有機材料として木材などの天然材料を使用していた時代に革命が起こったのです。この製造法は、鉄鉱石を高温還元して鉄原子塊である鉄鋼を製造するのとは大きく異なり、低分子の有機物質から高分子素材を製造するという人類の快挙でありました。それ以降は高分子化学が台頭して化学産業の発展につながり、数多の高分子が発明されてプラスチック材料の大量生産が可能になりました。現在では世界で年間1億数千万トンものプラスチックが生産され、嵩高さでは鉄鋼の総生産量に匹敵するまでにいたりました。
いっぽう、プラスチックの大発明から約150年後の2050年に向けて、著しく増加するプラスチック生産量を賄う原料資源の調達はかなり困難になると考えられています。有限量の化石資源に代わると考えられてきたバイオマス資源も現在の巨大な需要量の僅かな部分しか補えず、いっぽう世界的規模でCO2排出削減の制約も受けるでしょう。この将来社会において合成高分子の材料調達はリサイクルも含めて今後どのように変化し、また変えなければならないのでしょうか。
高分子とプラスチックの製造使用に関る者、リサイクルにより資源再生にかかわる者が協力して、2050年の社会を目標に置き議論する必要を強く感じます。そこでは、2050年に必要とされるプラスチックをどう作りどう使うのか、資源の再生に欠かせないリサイクル技術と社会のネットワークを含めて自由な議論を行い、将来のプラスチック社会の姿を真剣に見つめなければなりません。
さまざまな立場からのお考えとご意見を聞かせていただきたく存じます。
記:
1.FSRJと高分子学会GC部会がコアとなって共同発議し、集会準備会を立ち上げる。本年2013年の秋を目標に準備を進めたらどうか。
2.この合同企画は技術的研究集会とは別個に考えるのか、それとも関連させて考えるのか。
3.毎年1回は開催したらどうか。
Posted by FSRJ at 20:33│Comments(2)
この記事へのコメント
幹事会に出られませんので、メールにて失礼いたします。プラスチックから少し話が大きくなりますが、私自身も追いつけ追い越せの時代の終焉とともに、物まねが得意であった(?)日本人が、将来的に進むべき方向を見失って久しいと思います。それは産業のみで無く、政治、外交、社会等あらゆる方面にわたっています。例えば我国の都市の将来像やエネルギー需給の将来像を描こうとしても、中国・ロシア・韓国等の隣国との関係、TPP問題、EU問題、赤字国債問題、少子高齢化の行く末、地震等の災害、原発を含むエネルギー問題、等の影響パラメーターが多すぎて、考えれば考える程頭が混乱するばかりです。今少しでも頭を整理して、何か将来ビジョンを描けるように、世界と日本の地理並びに歴史を見返しながら考えようとしています。
つまり奥先生ご提案の鉄やプラスチックの将来像の研究会のご提案はもちろん大賛成ですが、その場合に鉄、プラスチックというような素材、つまりシーズから考える事プラス世の中の将来像を描きながら(難しいですが)、その中で鉄やプラスチックがどのような役に立つかというニーズからの掘り下げも同時に行うことが望ましいと考えます(もちろん先生のご提案にもこの趣旨は織り込み済みですが、改めて強調させて頂きました)。よろしくお願いいたします。
つまり奥先生ご提案の鉄やプラスチックの将来像の研究会のご提案はもちろん大賛成ですが、その場合に鉄、プラスチックというような素材、つまりシーズから考える事プラス世の中の将来像を描きながら(難しいですが)、その中で鉄やプラスチックがどのような役に立つかというニーズからの掘り下げも同時に行うことが望ましいと考えます(もちろん先生のご提案にもこの趣旨は織り込み済みですが、改めて強調させて頂きました)。よろしくお願いいたします。
Posted by 中込 at 2013年03月31日 08:43
市場の製品のほとんどは、混ざり具合の違いはあれどプラとそれ以外の材料との混合物であることはいうまでもあれいません。FSRJのメンバーも基礎レベルではプラに焦点を絞った研究をしていますが、その中での上記の視点をもって研究されてることが非常に多くなってきています。つまり、金属のみを対象したメタラジー分野の研究者とは違って、プラもきちんと視野に入れていると感じています。その結果、単に研究費が付きやすいからといってWEEEや自動車プラのリサイクル研究をしていないということです。そのあたりを強調するスタンスが必要と思っています。特に、今年の4月から動き出す小型家電リサイクルは、最終的には金属のリサイクルがメインで、それを支えるためにもプラのリサイクルが必要との見通してす。それらを踏まえて、将来への道筋を技術と哲学の視点からアプローチすることが不可欠でしょう。
Posted by 吉岡 at 2013年03月31日 08:45
コメントフォーム